本記事では分離多項式の定義と、その同値な言い換えについて解説します。
定義
定義は以下の通りです。
\(K\)を体とし、\(\overline K\)をその代数閉包とする。多項式\(f(X)\in K[X]\)が\(\overline K[X]\)において重根を持たない、すなわち$$f(X)=c(X-c_1)\cdots(X-c_n)\:\:\:(c_i\in\overline K)$$と分解したとき$$i\neq j\Rightarrow c_i\neq c_j$$が成立するとき、\(f(X)\)は分離多項式あるいは分離的であるという。
\(K=\mathbb{Q}\)の場合に少し例を見てみましょう。
分離多項式の例
- \(X-1\quad\)(一次式は当然分離的)
- \(X^2+1\quad\)(\((X+i)(X-i)\)と分解できる)
非分離多項式の例
- \(X^2-2X+1\quad\)(\((X-1)^2\)と分解できる)
- \(X^3+X^2-X-1\quad\)((\(X+1)^2(X-1)\)と分解できる)
このように、多項式が分離的かどうかを定義通り確認するには因数分解する必要があるのですが、一般の環上だとなかなか大変です。なので分離性を判定できる性質があればとても嬉しいですね。
性質1
実は次のような性質が成り立ちます。
\(K\)を体とし\(f(X)\in K[X]\)とすると、以下は同値。\begin{align}&(1)\quad f(X)\text{は分離多項式}\\[5pt]&(2)\quad f(X)とf'(X)はK[X]の中で互いに素\end{align}ここで\(f'(X)\)は\(f(X)\)の形式微分である。
(証明)
(1)\(\Rightarrow\)(2) 対偶を示す。\(f(X)\)と\(f'(X)\)が互いに素でないとすると、\(f(X)\)と\(f'(X)\)をともに割り切る一次以上の多項式\(g(X)\in K[X]\)が存在する。\(g(X)\)の根を一つ取り\(a\in \overline K\)とおくと、\(a\)は\(f(X),f'(X)\)の根でもある:\[f(a)=f'(a)=0\]ここで\(a\)が\(f(X)\)の重根でないと仮定する。すると\[f(X)=(X-a)h(X)\quad(h(X)\in \overline K[X])\]と表したとき、\(h(a)\neq0\)となる。ここで形式微分のライプニッツ則より\[f'(X)=h(X)+(X-a)h'(X)\]が成立するので、これに\(a\)を代入することで\[f'(a)=h(a)\neq0\]となるが、これは\(a\)が\(f'(X)\)の根であることに矛盾。従って\(a\)は\(f\)の重根であり、\(f\)は分離多項式ではない。
(1)\(\Leftarrow\)(2)\(f(X)\)と\(f'(X)\)が互いに素であるとすると、ある\(g(X),h(X)\in K[X]\)が存在し、\[g(X)f(X)+h(X)f'(X)=1\]となる(ベズーの等式)。ここで\(f(X)\)に重根が存在したと仮定し、それを\(a\in \overline K\)とおくと、\(f(X)\)は\[f(X)=(X-a)^2i(X)\quad(i(X)\in \overline K[X])\]と表せる。形式微分のライプニッツ則より、\[f'(X)=2(X-a)i(X)+(X-a)^2i'(X)\]が成立するので、これに\(a\)を代入することで\[f'(a)=0\]を得る。よって上の等式から\[1=g(a)f(a)+h(a)f'(a)=0\]となるがこれは矛盾である。従って\(f\)に重根は存在せず、\(f\)は分離多項式である。
(証明終)
性質2
既約多項式についてはさらに良い性質があります。
\(K\)を体とし、\(f(X)\in K[X]\)を\(K[X]\)で既約な多項式とする。このとき以下は同値\begin{align}(1) &f(X)は分離的でない\\[5pt](2) &f'(X)=0\\[5pt](3)&Kは正標数:\text{ch}K=p>0かつ\\&既約な分離多項式g(X)とr\geq1によってf(X)=g(X^{p^r})と表せる。\end{align}
(証明)
(1)\(\Rightarrow\)(2)上の性質1から、\(f\)と\(f’\)は互いに素でない。従ってこれらをともに割り切る素元(すなわち既約多項式)\(g\in K[X]\)が存在する。いま\(f\)は既約なので\(f\)は\(g\)の単元倍、すなわち定数倍であることが分かる。よって\[f(X)=cg(X),f'(X)=g(X)h(X)\quad(c\in K^{\times},h(X)\in K[X])\]などとおくと\[f'(X)=\frac{1}{c}f(X)h(X)\]となり、\(f’\)が\(f\)で割り切れることが分かる。よって\(f’\neq0\)と仮定すると\[\deg f’\geq \deg f\]となるが、形式微分の定義から明らかに\[\deg f'<\deg f\]なので矛盾。従って\(f’=0\)である。
(1)\(\Leftarrow\)(2)\(f’=0\)とすると\(f\)と\(f’\)は互いに素とはなり得ないので性質1から\(f\)は分離多項式である。
(2)\(\Rightarrow\)(3)\[f(X)=a_nX^n+\cdots+a_1X+a_0\]とおく。\[f'(X)=na_nX^{n-1}+\cdots+2a_2X+a_1=0\]より、\(k=1,\dots,n\)に対し\[ka_k=0\]が成立する。ここで\(K\)の標数を\(0\)と仮定すると、\(k=1,\dots,n\)に対し\[a_k=0\]となり、\(f(X)=a_0\)となるが、これは\(f\)が既約多項式であることに矛盾。従って\(K\)は正標数であり、その標数を\(p\)とおく。\(p\)と互いに素な\(k\)に対しては、\(ka_k=0\)から\(a_k=0\)が従うので結局\(a_k\neq0\)となり得る\(k\)は\(p\)の倍数のみ。従って\(f\)は\[f(X)=a_{mp}X^{mp}+\cdots+a_pX^p+a_0\]と表せる。よって\[f_1(X):=a_{mp}X^m+\cdots+a_pX+a_0\]とおくと、\[f(X)=f_1(X^p),\deg f>\deg f_1\]が成立する。この等式から、\(f_1\)が可約だと仮定すると\(f\)も可約となり矛盾するので、\(f_1\)は既約。もし\(f_1\)が分離的でないなら、上で示したように\(f’_1(X)=0\)となるので、同様の操作を行い、\[f_1(X)=f_2(X^p),\deg f_1>\deg f_2\]なる既約多項式\(f_2\in K[X]\)を取ることができる。これを繰り返すと、\[\deg f>\deg f_1>\deg f_2>\cdots\]と、次数が真に減少していくので、この操作が無限に繰り返されることはなく、必ず有限回で止まる。よってある\(r\geq1\)が存在し、\(f_r\)は既約な分離多項式となり、\[f(X)=f_1(X^p)=f_2(X^{p^2})=\cdots=f_r(X^{p^r})\]が成立する。
(2)\(\Leftarrow\)(3)\[f'(X)=(g(X^{p^r}))’=p^rX^{p^r-1}g'(X^{p^r})=0\]よりOK
(証明終)
(1)と(3)から、既約な分離多項式は正標数の場合にしか存在しないことが分かります。このことからすぐに、標数0の体は完全体であることが従います。このあたりのことも今後紹介予定です。


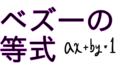
コメント